雛人形をいつ飾ればよいのか、時期やお日柄は関係ある?
旧暦でお祝いする地域もありますが、季節の節目である立春(2月4日)頃から雨水(うすい・2月19日)頃までの間に雛人形を飾るのが一般的でしょう。雛祭りは桃の節句ですので、立春のタイミングが良いでしょう。
また、「鬼は外」で馴染み深い節分が、2月3日にあたります。節分は鬼を祓う(退治する)行事のため、鬼を祓ってから飾りましょう、といった意味合いから、2月4日以降が、雛人形を飾る適切なシーズンとされています。
「1月から飾ってはダメなのか?」というご質問もいただきます。これは、三ヶ月に渡って飾り続ける、三月がけ(みつきがけ)にあたるので、縁起が悪いと考える方も少なくないです。
しかし昨今の生活事情から、三月がけを気にされない方も多いです。「綺麗なお雛さまを長い間飾りたい」といったご意見を尊重すべく、倉片人形でも三月がけについては特に言及しておりません。あくまでも歴史や文化なので、目安と考えていただいて結構です。
また日本では、古くから六曜(先勝,友引,先負,仏滅,大安,赤口)でその日の吉凶を占ってきました。六曜を意識して雛人形をお飾りになる場合は、大安、友引の日を選んで飾られると良いでしょう。
雛人形は湿気に弱いですが、飾る日の天候などは特に気にされなくても問題ありませんので、2月4日以降の大安、友引の都合の良い日に飾られるのがベストです。
2021年〜2025年で雛人形を飾る日が具体的にはいつなのか紹介
| 西暦 | ベストな日 |
| 2021年 | 2月5日(金) 2月8日(月) 2月11日(木) 2月13日(土) 2月16日(火) 2月19日(金) |
| 2022年 | 2月5日(土) 2月8日(火) 2月11日(金) 2月14日(月) 2月17日(木) |
| 2023年 | 2月4日(土) 2月7日(火) 2月10日(金) 2月13日(月) 2月16日(木) 2月19日(日) |
| 2024年 | 2月3日(土) 2月6日(火) 2月9日(金) 2月11日(日) 2月14日(水) |
| 2025年 | 2月5日(水) 2月8日(土) 2月11日(火) 2月14日(金) 2月17日(月) |
雛人形はいつまで飾る?どの時期にしまうのがよいのか説明します
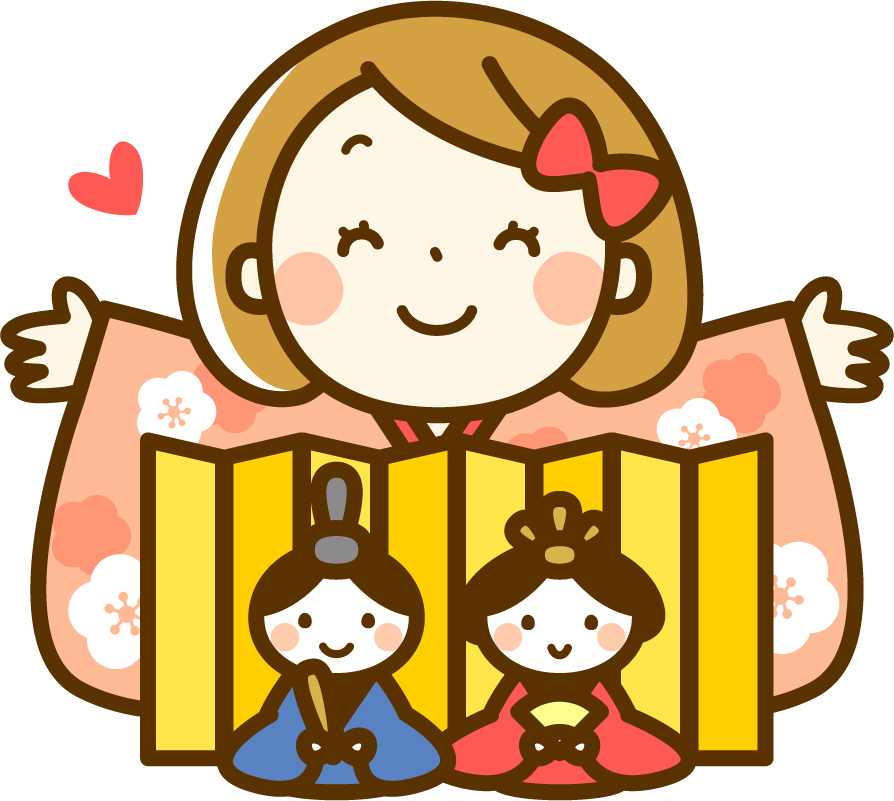
よく「雛人形をしまうのが遅くなるとお嫁にいけなくなる」と言いますが、そんなことはありません。片付けが出来ない人にならないように、つまり「しつけ」の意味の言葉の例えということです。
では、しまうのはいつが良いかと言いますと、3月中旬頃の天気の良い乾燥した日にしまうのが良いでしょう。それでは、しまい方を詳しく説明していきます。
目安として、雛人形は啓蟄(けいちつ・3月6日)頃に片付けると良いでしょう。そもそもお節句とは、「子供が無事に成長し、立派な大人に育つように」という、人生の節目を祝うお祭りです。できるだけ季節の節目を超えずになるべく早く片付けることを心がけましょう。
一方で雛人形は湿気に弱いため、天気の良い乾燥した日に片付けていただきたいです。縁起の良い日を意識するよりも、人形に優しい晴れた日を選んで片付けすることが最も重要です。
ちなみに、「雛人形をしまうのが遅くなるとお嫁にいけなくなる」と言いますが、これは片付けができない人にならないように、「しつけ」の意味合いから生まれたフレーズでした。
雛人形は、天気の良い乾燥した日に、なるべく早く片付けましょう。
雛人形のしまい方・片付け方を紹介します
白手袋・毛ばたき・柔らかい布・人形用防虫剤を準備します。

毛ばたきでお人形やお道具のホコリを払います。

手袋をしてお人形が持っている持道具を外します。

飾り台、屏風のホコリや指紋を布で拭き取ります。

お人形の顔を顔紙で包む。最初に顔を包んでいた顔紙が無くなってしまった場合は、ティッシュなど柔らかい紙で包んで下さい。

お人形やお道具、飾り台、屏風を入っていた箱に入れる。飾る前に、入っていた状態の写真を撮っておくとしまう際に便利です。

人形用防虫剤をお人形やぼんぼり、お花の箱に入れます。

箱は湿気のない場所に保管しましょう
毎年きれいな状態で飾れるように、しっかりとホコリや汚れを取り、湿気のない場所に保管することが大事ですね。お子様が大きくなったら楽しみながら一緒に飾り一緒にしまって下さい!
修理や単品購入もできる倉片人形にご相談ください
雛人形を飾る日やしまう日以外にも、雛人形をに関してわからないことや悩んでしまうことがあると思います。そんな時は倉片人形におまかせください。倉片人形には多くの雛人形職人が在籍しており、豊富な知識と技術力でお客様をサポート致します。
百貨店や通常の専門店では、飾台や屏風、雪洞(ぼんぼり)と人形をセットで販売しています。倉片人形では、飾台や屏風、雪洞、人形など、雛人形を構成するパーツ全てを単品購入できます。オンラインショップに掲載されている商品は一部商品を除いて単品購入ができます。
一部壊れてしまったから修理したい、新しくしたいなどのご相談も受け付けております。もちろん、他店でご購入された場合でもご相談くださいませ。
店舗では時期になると300種類以上の節句人形を販売します。他店には負けない商品数とサポートで全国の皆様から愛される企業を目指しております。
自由に組み換えできる、雛人形の専門店は倉片人形
倉片人形は、埼玉県所沢市で雛人形を作り続けて180年の歴史ある節句人形店です。同敷地内に制作工房があり毎日雛人形を制作しております。
倉片人形の店舗では300種類以上のお雛様が展示されており、その規模は全国最大級なことで有名です。
倉片人形では、雛人形や飾台、屏風を自由に組み替えて購入することができる「カスタマイズ販売」に力を入れております。
一生に一度の大切なお守りですので、妥協のないお雛様選びをしていただきたいという思いからカスタマイズ販売を行っています。
また遠方で来店が難しい方にはLINEのやりとりでもカスタマイズ販売をご案内できますので、まずは一度お問い合わせくださいませ!














